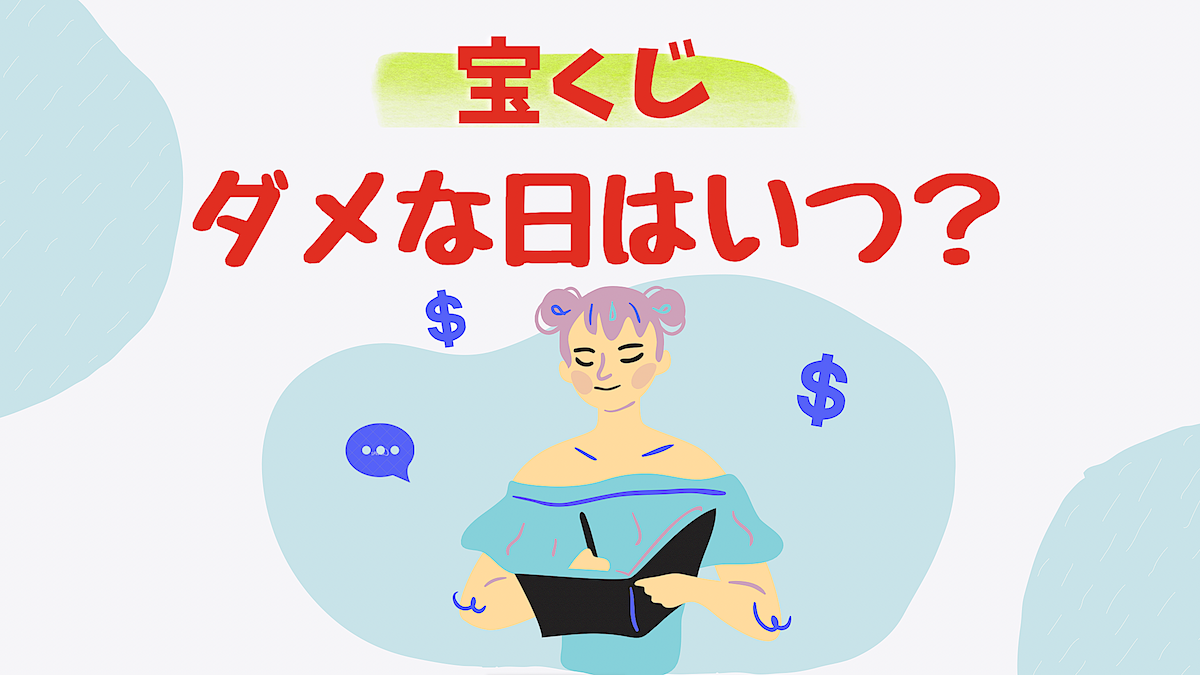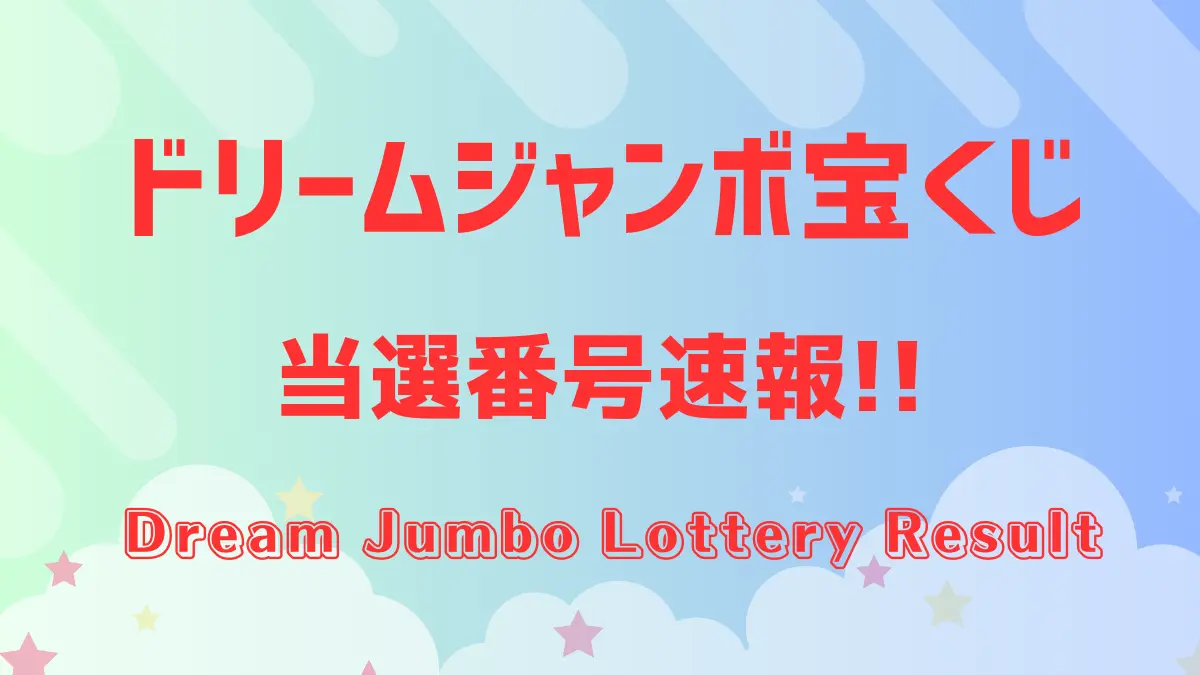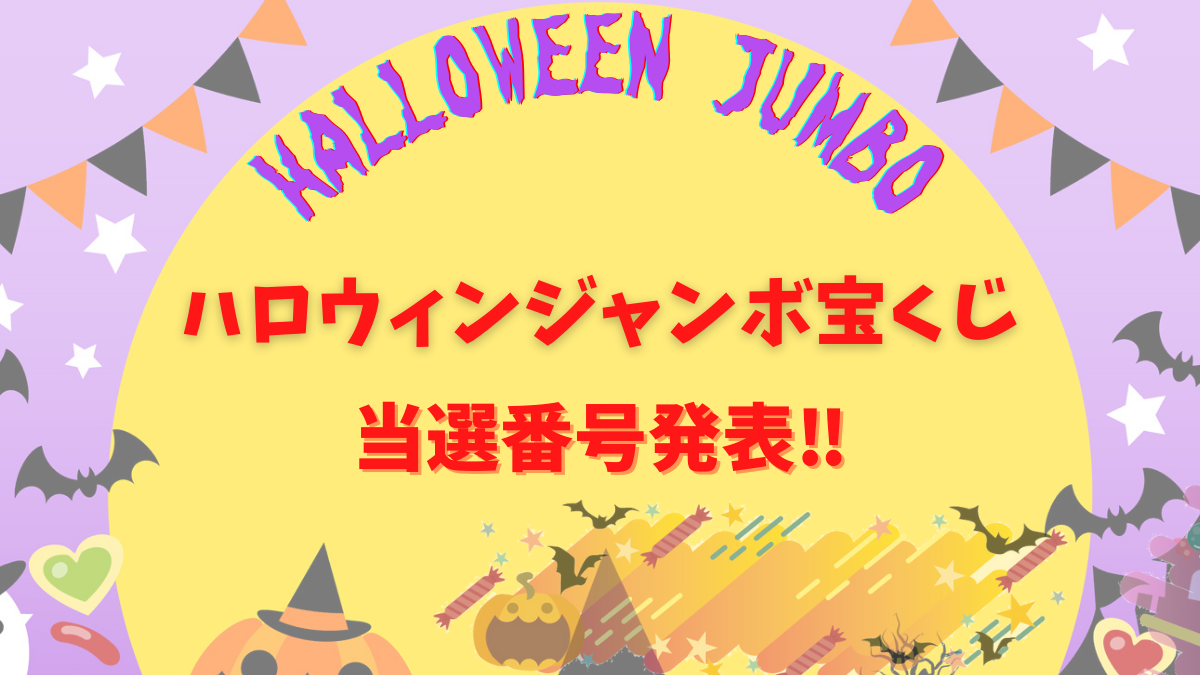晦日祓い(みそかばらい)とお正月飾りの時期とやり方
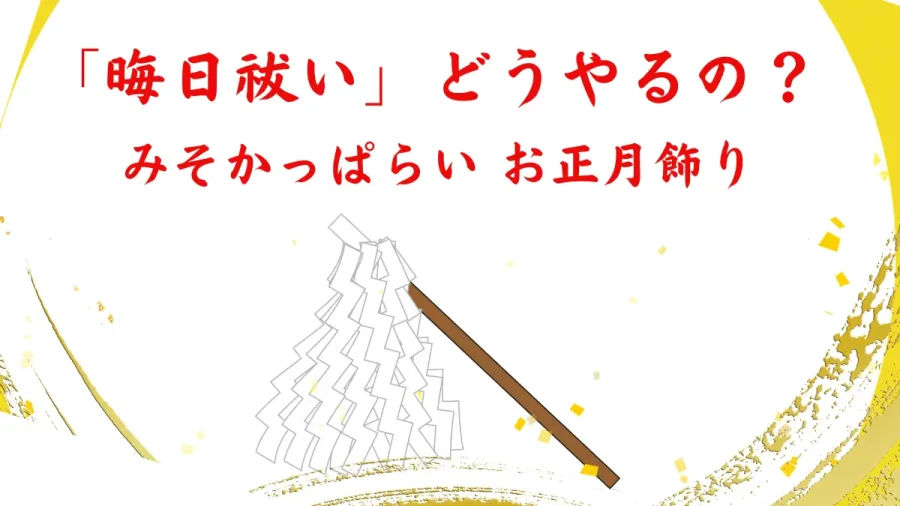
「みそか祓い」って何?どうやるの?
お正月飾りはいつ飾りつけるといいの?
お正月飾りを外す時期はいつ頃?
外した後はどうすればいい?
ここではこんな疑問の答えを、わかりやすく解説します。
日本ではお正月を迎えるにあたり、師走に入ると様々な準備を始めます。
いつ何をどうしたらいいのかを確認して、良い年越しと新しい年の始まりを迎えましょう。
ちなみに読み方は「みそかばらい」や「みそかっぱらい」と地域性もあります。
お正月飾りについて
まず大前提として、お正月飾りをする前に大掃除を済ませて下さい。
風水や開運などに興味のある方でしたら、普段から掃除は行き届いていると思いますが、普段できない所もきれいにしてスッキリしましょう。
お正月飾りを始める時期と外す時期
目安としては12月の26日〜28日・30日のあたりに飾り付けます。
この時期の暦を確認して「赤口」「仏滅」を避けて日にちを選びましょう。
外す時期は「松の内」と呼ばれる1月7日までにしましょう。
お正月の飾りつけを避けるべき日に注意
お正月の飾り付けをする日で、避けた方がいい日はいつかをご紹介します。
- 29日は「二重苦」や「苦がまつ(末)」と言われ避けられています
- 31日は「一夜飾り」となってしまうので、年神様をお迎えするにはふさわしくありません
(地域によって様々ですので参考までに)
門松の飾り方と時期
門松は、家の門や玄関前の左右に1本ずつ飾るのが一般的です。
こちらもお正月飾りと同じで26・27・28日もしくは30日に飾り、松の内(1/7)までに外しましょう。
※これは地域により様々で、15日まで飾る風習の所もあります。
しめ縄の飾り方と時期
しめ縄も門松と同じです。
門松、しめ縄同じ日に飾るとよいでしょう。
外す時期も門松と同じですので、一緒に下げましょう。
鏡餅の飾り方と時期
鏡餅は、13日~28日にお供えするのがいいそうです。
オススメは「28日」です。
28日は末広がりの八がついており特に縁起が良いとされています。
鏡餅は1月11日の鏡開きに下げ、家族でそのお餅を食べましょう。
お正月飾りの片付け方
門松やしめ縄と同じく松の内(1/7)までに外します。
外したら、紙袋などに入れ丁寧にひとまとめにしましょう。
大きいものは新聞紙で包むとよいでしょう。
外したお正月飾りは、1月15日(小正月)の行事「どんど焼き」で!
「どんど焼き」とは、正月飾りとして使ったものを、集めて火にくべる行事です。
お正月飾りと、古いお札やお守りも一緒で大丈夫です。
どんど焼きは、神社で神事として行いますが、地域の行事として行うこともあります。
ちなみに我が家では、近くの神社で行われる「どんど焼き」でお世話になっています。
おさめられる場所が用意されており、たくさんの方が利用しています。
(どんど焼きの火にあたると一年健康でいられると言われています)
どんど焼きに出せなかった時はどうしたらいい?
新聞紙などで丁寧に包み、自治体の定めるゴミの処分に従って出して下さい。
晦日祓いってどうやったらいいの?

「みそか祓い」とは、大晦日に家のお祓いをすることです。
大掃除のときは必ず神棚をきれいにして下さいね。
(大掃除の後にお正月飾りをするので、早めに大掃除を始めるといいですよ)
「みそかっぱらい」プチ情報
ある地域では年越しそばの代わりにけんちん汁を頂く風習があり、食後に「味噌をかっぱらってお祓いをする・・・」というような語源があるとか?
晦日払いをしよう
神社によっては「晦日払い」の一式を購入できるので、用意するとより有難みが増します。
(千円程度〜で用意できます)
- 神棚にお供えした祓え串で神棚をお祓いし清めましょう
- 家の代表者が祓え串で家中の全室、そして家族をお祓いします
お祓いの方法
左・右・左と祓え串で三度振ります。
それを、神棚と各部屋、家族に行います。
全て終えたら、祓え串を家の外の鬼門の方向(北東か南東)の土に立て、そのまま片付けないのが習わしとなっています。
(祓い串についた悪いものを外に出す「鬼門除け」の意味があるのだそう)
家族でお祓いをして新しい年を迎えましょう。
以上は一般的に言われている内容をまとめて紹介したものです。
地域によっていろんな風習が様々ありますので、どれが正しいとか間違いとかではなく、そうする意味を考えてみてはいかがでしょうか。
新年を迎えるにあたり、無事であった事を感謝し、悪い事があったならお祓いをし、新しい一年が良い年でありますように。
そんな気持ちで年末年始を過ごすのが、日本のお正月ではないでしょうか。
よいお年をお迎えください🌅

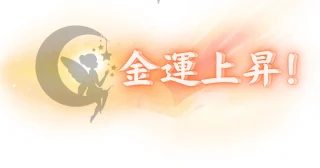
![200円が万倍越え!?[天赦日]+[一粒万倍日]は最強だった!](https://hetarechan.com/wp-content/uploads/2022/03/2m.webp)